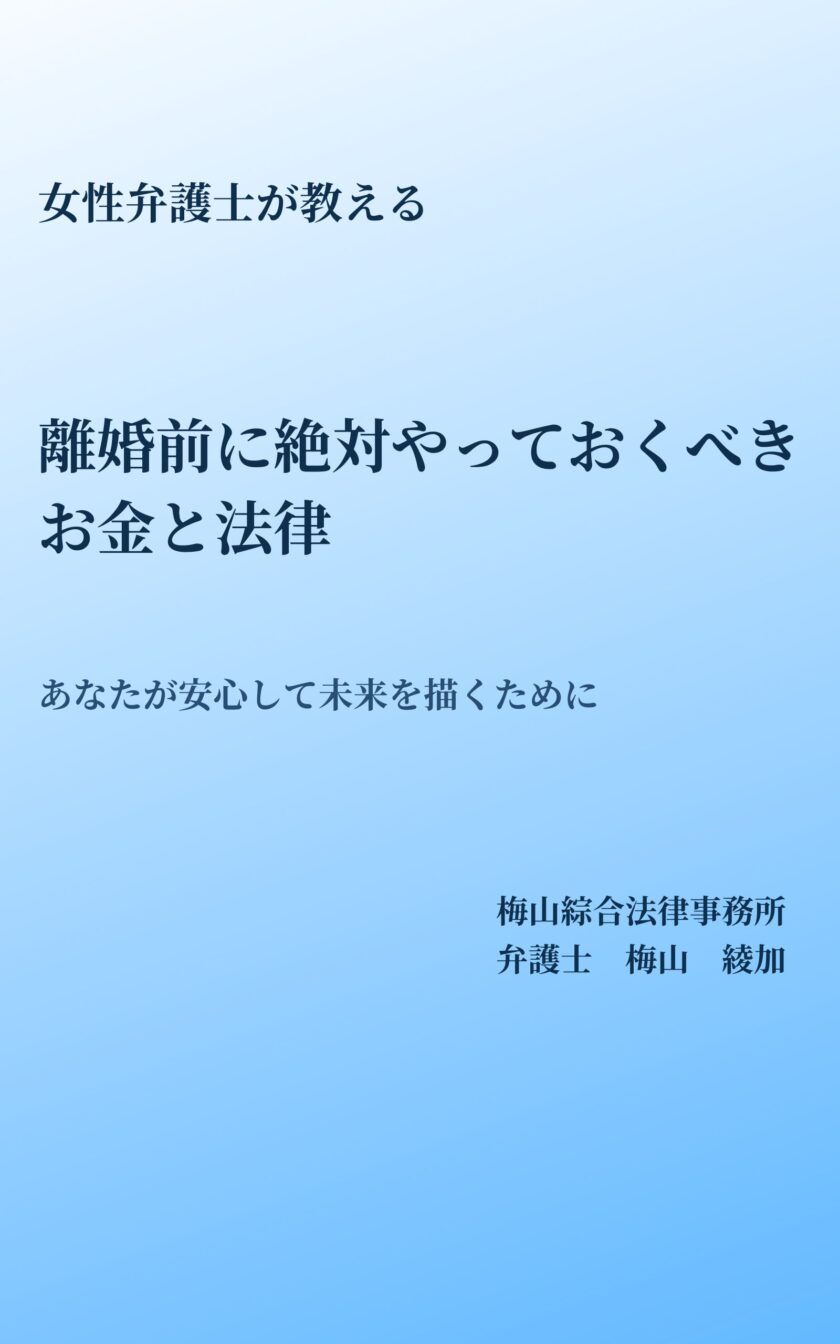「女性弁護士が教える 離婚前に絶対やっておくべきお金と法律」のご紹介
梅山綜合法律事務所の弁護士・梅山綾加です。
このたび、離婚を考えている方・迷っている方に向けて、
お金と法律の基礎知識をわかりやすくまとめた書籍を出版いたしました。
「感情だけで離婚を決めて後悔してほしくない」
「知っていれば守れたはずのお金や権利を、きちんと守ってほしい」
そんな思いから執筆した一冊です。離婚を具体的に考えている方はもちろん、
「いつか離婚するかもしれない…」と漠然と不安を感じている方にも役立つ内容になっています。
書籍出版のお知らせ
このたび、2025年10月29日に
『女性弁護士が教える 離婚前に絶対やっておくべきお金と法律】』
を【Amazon Kindle】から発売いたしました。
離婚相談を受けてきた現役の弁護士として、
「相談前に、最低限ここだけは知っておいてほしい」というポイントを
できるだけやさしい言葉でまとめています。
この本でわかること
本書では、次のような疑問にお答えしています。
・離婚を考える前の“見るべきチェックポイント”
・慰謝料・財産分与・年金分割の仕組みと注意点
・預貯金・不動産・借金など資産の洗い出し方法
・離婚後にしなければならない手続と生活再建
・離婚協議書・公正証書の作り方を注意すべきポイントを踏まえて解説
・子どもがいる場合の親権・養育費・面会交流の基本
・弁護士への相談のタイミングと、費用の基本
法律用語の解説だけでなく、
実際の相談現場でよくある「勘違い」や「後悔のパターン」も紹介しています。
本の特徴
- 現役の女性弁護士が執筆
実際の離婚事件を扱ってきた経験から、
現場で本当に問題になりやすいポイントに絞って解説しています。 - 専門用語をなるべく使わない、やさしい文章
法律の本は難しいイメージがありますが、
法律に詳しくない方でも読み進められるよう、具体例を交えて説明しています。
こんな方におすすめです
- 配偶者との関係に悩み、離婚すべきかどうか迷っている方
- 離婚を決意したものの、何から手をつければいいのかわからない方
- 子どもがいて、養育費や面会交流について不安がある方
- 専業主婦(専業主夫)やパート勤務で、
「離婚した後、本当に生活していけるのか」と心配な方 - インターネットの情報が多すぎて、何を信じればよいかわからなくなっている方
ご購入方法
書籍は、以下からご購入いただけます。
- 【女性弁護士が教える 離婚前に絶対やっておくべきお金と法律(amazon Kindle版)】
著者からのメッセージ
離婚は、人生の中でも大きな決断のひとつです。
その一方で、勢いで話を進めてしまったり、相手のペースに流されてしまったりすると、
後から取り返しのつかない不利益を被ってしまうこともあります。
私は、これまで多くのご相談をお受けする中で、
「もっと早く相談していれば、もっと違う選択肢があったのに…」と感じる場面を何度も見てきました。
この本が、
「感情だけでなく、情報と準備をもって、自分と子どもの未来を守るための一歩」
になれば嬉しく思います。
書籍を読まれた方へ ― 個別相談のご案内
本書は、離婚に関する全体像をつかんでいただくためのガイドブックです。
ただし、実際の最適な解決方法は、ご家庭の状況によって大きく異なります。
- 自分の場合、どのような進め方が良いのか
- 相手が応じてくれないとき、どう対応したらよいのか
- 財産や子どものことについて、もっと具体的なアドバイスが欲しい
といった場合には、個別相談をご利用ください。
梅山綜合法律事務所では、離婚・男女問題に関するご相談を承っております。
- ご相談のご予約は、
お電話(【TEL:027-225-2356】)から可能です。 - 相談時には、資料(通帳のコピー、不動産資料、LINEやメールの画面など)をお持ちいただくと、
より具体的なアドバイスがしやすくなります。
おわりに
離婚は、決して「失敗」ではなく、
これからの人生をどう生きていくかを考えるための新しいスタートラインでもあります。
本書と当事務所でのご相談を通じて、
少しでも心が軽くなり、「自分らしい選択」ができる方が増えればと思っております。
今後とも、梅山綜合法律事務所をどうぞよろしくお願いいたします。